英語は比較的安定しやすい科目なので、英語を得意にすると受験において大きな武器になります。
私は現役時代数学が苦手で英語に頼っており、東大模試では最高で91点を取ったことがあります。
しかも、高校生になってからは予備校で英語の授業はほとんど取っていないので、実質独学といってもよいぐらいです。
そこで、今回は実際に東大に受かった英語の参考書ルートをお伝えしようと思います。
英語が安定すると合格率が段違いだよ!
 マトン
マトン数学よりも得点が安定しやすいから勉強しがいがあるぜ!
単語
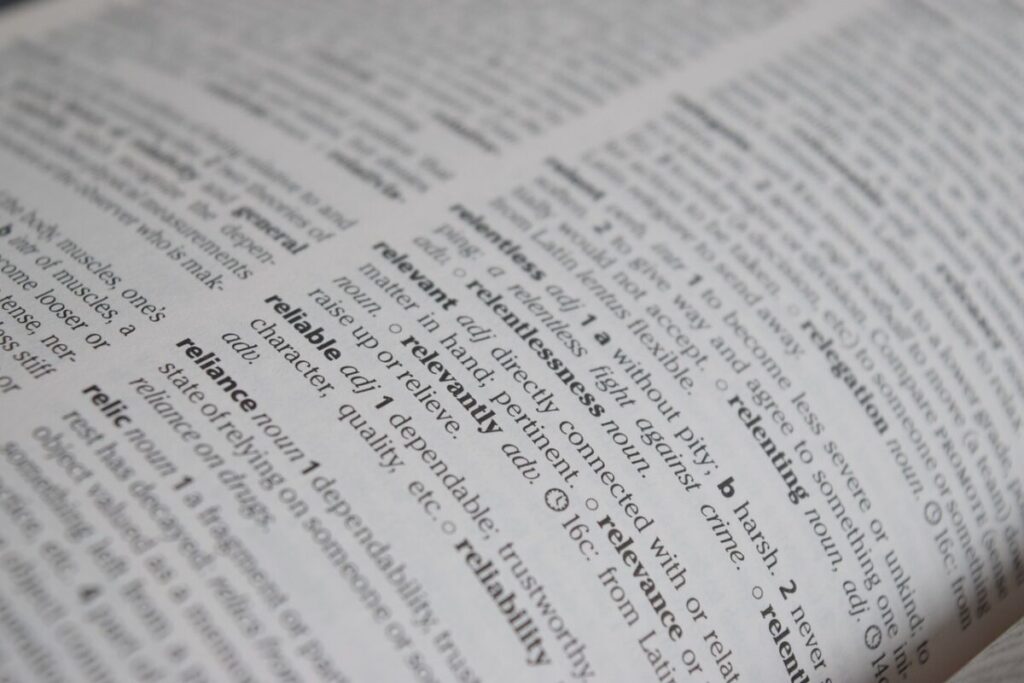
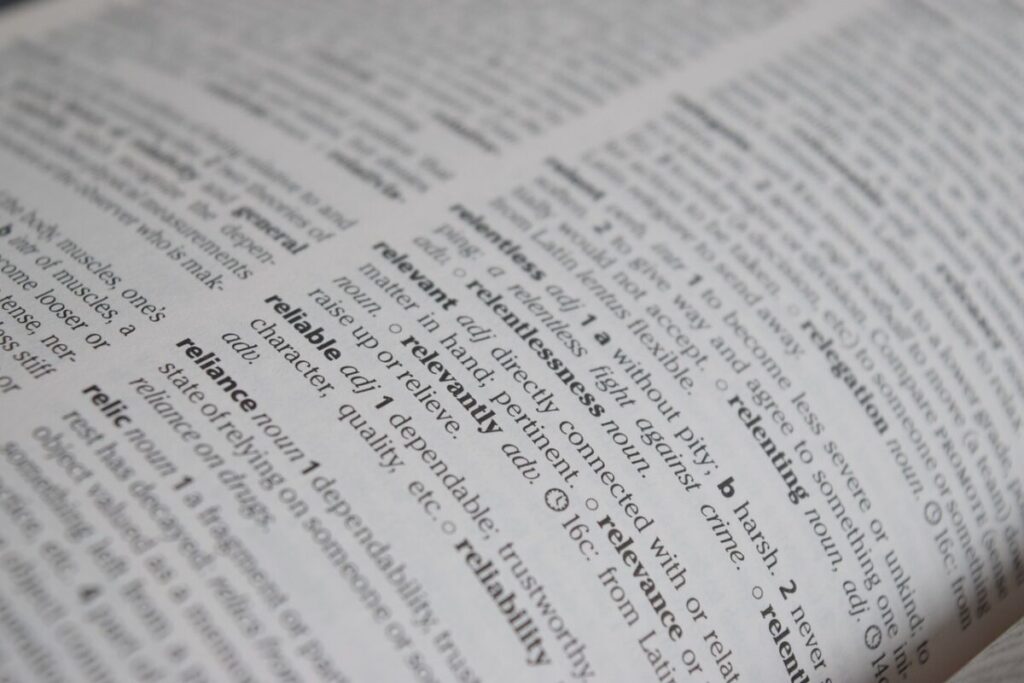
まず、単語が分からなければなにもできません。
単語は多く知っているに越したことはありませんが、受験生は時間がないので、何か一冊単語帳を完璧にすることを目標にしましょう。
また、単語は覚えてもしばらくすると忘れます。したがって、これから紹介していく学習と並行して、単語の学習は入試本番までずっと続けてください。
単語帳は簡単すぎない限りなんでもいいんですけど、ここでは私が使っていた単語帳を紹介します。
英単語を表すイラストが単語の横に描いてあったりテーマ別に単語が載っていたりと、覚えやすいように工夫されているのが特徴です。
掲載単語のレベルも東大英語にはちょうどよいので、迷ったらこれでOK。
文法
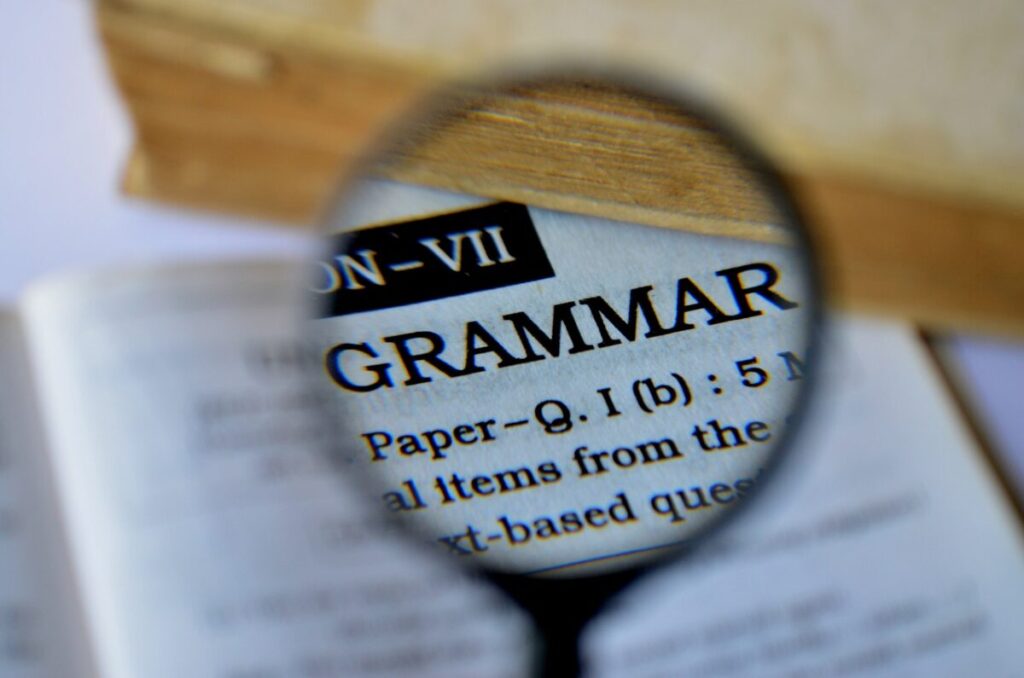
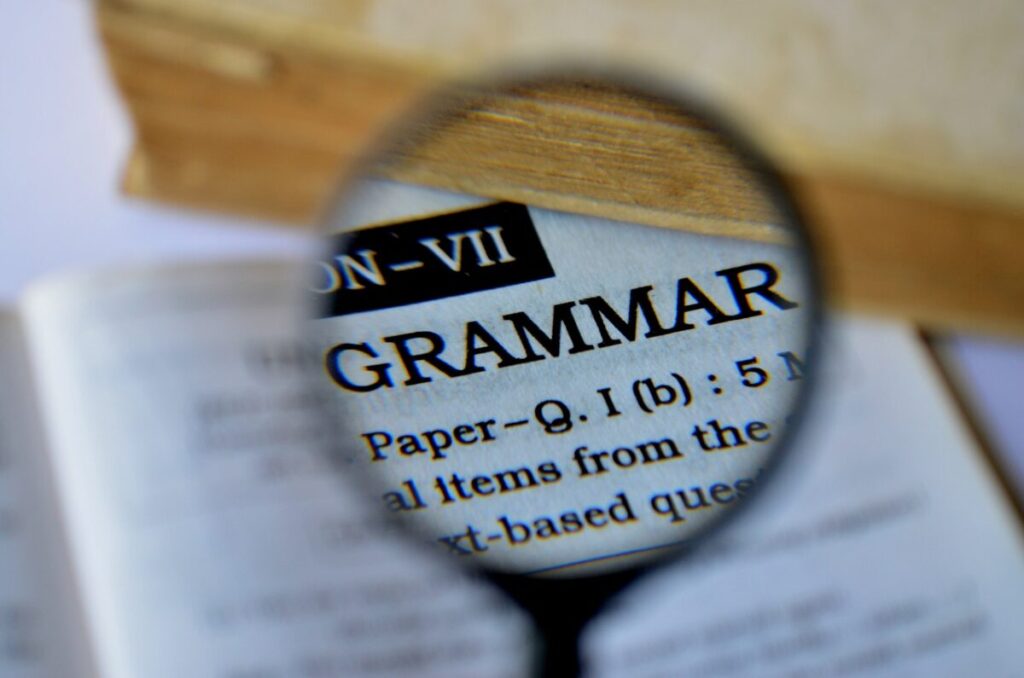
単語と並んで重要なのが、文法です。
ここまでをどれだけ早い時期にやれるかというのがとても重要です。
英文法の導入
参考書ルートの紹介なのに申し訳ないのですが、私は中学生の頃に文法を高校範囲まで塾で教わっていたため文法書はあまり読んだことがありません。
ただ、個人的には文法は授業で習った方が概観がつかみやすいと思います。
私と同じように授業で文法の基礎を固めるなら、スタディーサプリの関先生の英文法の授業を受けるとよいでしょう。
とても評判がよく、テレビでも紹介された授業です。
私も受験生のときスタディーサプリに登録していたので気になって少しのぞいてみたことがあったのですが、たしかに分かりやすい授業で、もし初学なら間違いなく利用していたと思います。
受験生なら知っている思いますが、スタディーサプリは値段がリクルートの力技で破格になっているので、うまく活用すると超絶コスパで勉強を進めることができます。
最初の14日間の無料期間を使って関先生の授業を覗いてみることをおすすめします。
【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座授業より参考書派なら学校で配られた文法書を使ってもいいので、とにかく勉強していない単元がある方は早急にすべてさらってしまいましょう。
問題集
問題集で確認すると知識が定着しやすいです。
私は学校で配られた「ネクステージ」という英文法の問題集を解いていました。
見開きで左側に問題があり、右側ではその問題で重要なポイントとなる文法について解説されています。
ただ、もし学校で「ヴィンテージ」などの他の文法問題集が配られているなら、わざわざ「ネクステージ」を買う必要はありません。
自分が持っている参考書で代用して大丈夫です。
和訳(英文解釈)


文法の学習が一通り済んだら、次は和訳の練習に入ります。
多くの人がこの練習をおろそかにして文章を速く読む練習に入るのですが、精読ができないと文章の内容が正確につかめないため、文章を目で追っているだけという状況になってしまいます。
共通テストならそれでもある程度の点が取れるかもしれませんが、二次試験ではそうはいきません。
逆に、精読が出来れば既にある程度のスピードで読めるようになっているはずなので、心配せずに和訳の練習を進めましょう。
また、東大では和訳の問題が出題されるので、東大受験生はどうせいずれ練習することになります。
それならばこのタイミングでやってしまった方がよいと思います。
和訳の練習には「基礎英文解釈の技術100」と「ポレポレ英文読解プロセス50」の2つに取り組みました。
どちらも名著で、やり込めば間違いなく読解力がつきます。
どちらもやる場合は、「基礎英文解釈の技術100」の方が簡単なのでそっちを先にやってください。
英作文
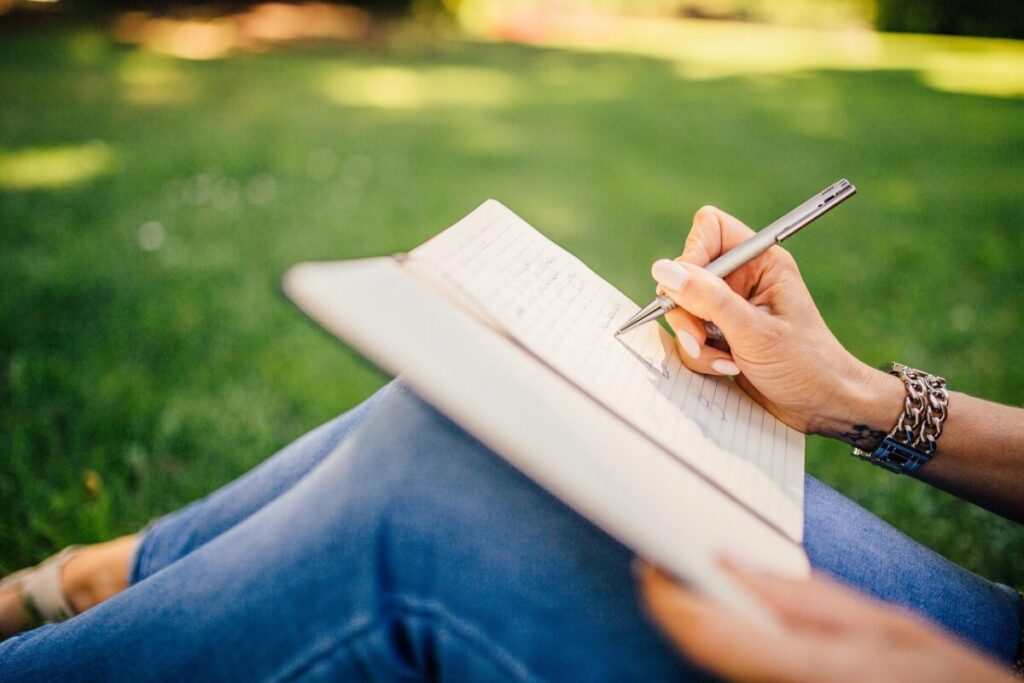
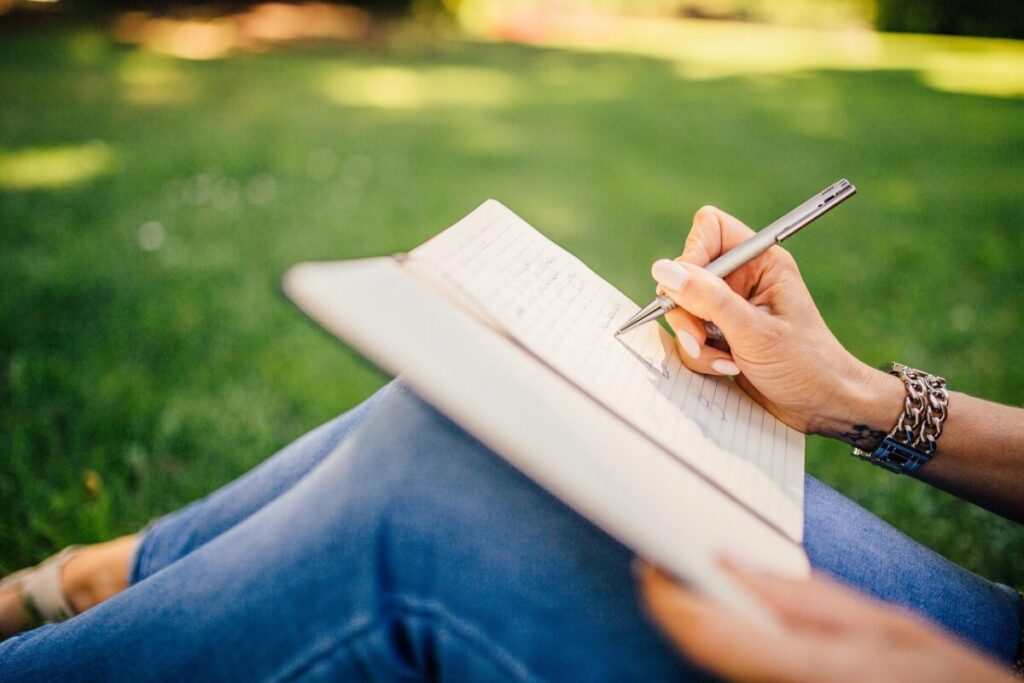
東大には英作文の問題が出題されるので、別途で対策が必要になります。
単語と文法さえ知っていれば英作文は書けるだろうと思っている方もいるかもしれませんが、言いたいことを効果的に文章に表すのは存外難しいです。
そのことは、一度英作文の問題を解いてみればわかるでしょう。
なぜ言いたいことがあっても書けないのかというと、幅広く使える表現を知らないからです。
単語には使える組み合わせというものがあり、難しい単語ほど使える場面が限られています。
しかしながら、用法が限られるからといって、様々な用法に対応するために難しい単語を山のように覚えている暇はないでしょう。
上の例では、代わりにtake (good) care ofを用いることで、ほぼすべてについて「大切にする」を表現することができます。
このように、簡単な表現で伝えたいことをできる限り伝える手法が紹介されているのが「竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本」という参考書です。
例題に加えて演習問題までついているので、正直英作文はこの一冊だけで十分で、他の本をやっている暇がないぐらいです。
リスニング


東大入試では共通テストだけでなく二次試験でリスニングが30点分も出題されるので無視するわけにはいきませんよね。
私はリスニングがとても苦手なのですが、練習してある程度の点なら取れるようになったので、今苦手な人も捨てないで少しは対策しておくとよいと思います。
私が使っていたのは、「キムタツの東大英語リスニング」という参考書です。
問題の難易度がちょうどいいので、この参考書を使って問題を解いて音読やシャドーイングを行うことで良い練習になると思います。
また、参考書ではないですが、TEDなどのネット上の素材を活用して毎日英語を聞くこともとても大切です。
過去問
上に書いた参考書で基本を押さえたら、実際に過去問を解いてみましょう。
時間制限なしならもう既にある程度解けるはずです。
もし全く解けないなら、上にあげた項目のどこかが抜けている可能性が高いので、もう一度やりなおす必要があります。
過去問に関しては、1年度分制限時間付きで解くのもよい練習になるし、いずれはそれも必要になります。
しかし、英語に関しては早くから普段の勉強を過去問に切り替えられる科目なので、よりハードルを下げて日常的に取り組めるようにするため、基本的には大問ごとに取り組むのがおすすめです。
「東大の英語25カ年」はまさに大問ごとに解くための参考書で、私は秋~冬にかけてこの本をやりこみました。
この本に載っている問題をどんどん解いて、英語そのものにも東大の問題にも慣れていきましょう。
なお、年度ごとの演習をするときのために、直近10年は残しておくとよいです。
長文の参考書はやらなくていいの??



私は長文の参考書は学校の授業で扱ったもの以外使いませんでした。
どうせ長文を読むなら、過去問の傾向対策も同時に行った方が効率が良いからです。
短めの文で練習したいなら、東大英語には1(a)という最適な大問が用意されています。
各大問でどんな問題が出るのか知りたい方は、以下の記事を参考にどうぞ。
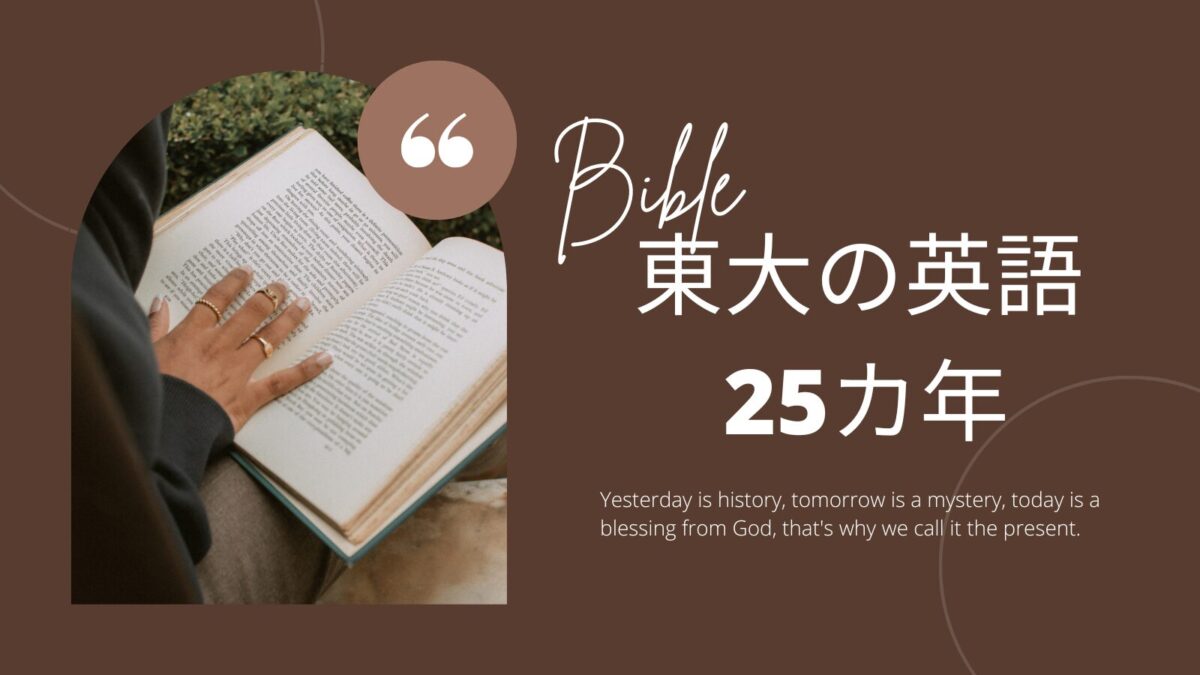
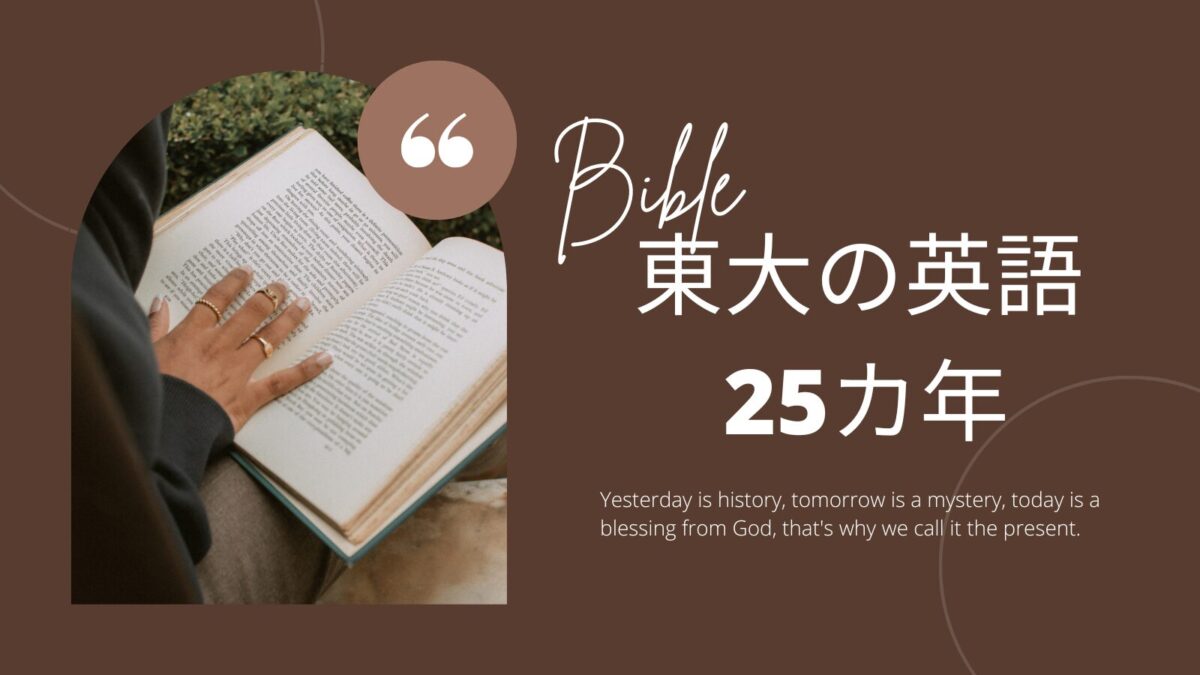
まとめ


上図は東大英語対策の大まかなフローです。(参考書等は代表的なものを表示しています。)
まとめると、
文法→和訳→英作文,リスニング,過去問
※単語は最初から最後まで勉強し続ける
というルートで学習を進めるのがよく、それぞれの段階でのおすすめ参考書は、
単語・・・東大英単語熟語鉄壁
文法・・・スタディーサプリ(参考書ではないですが),ネクステージ
和訳・・・基礎英文解釈の技術100,ポレポレ英文読解プロセス50
英作文・・・竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本
リスニング・・・キムタツの東大英語リスニング
過去問・・・東大の英語25か年
が挙げられます。
英語を安定させると東大模試の判定も安定感が出てくるので、ぜひこれを参考に英語学習を頑張ってください。
LINE公式アカウントのご紹介
当ブログのLINE公式アカウントでは、受験生の方にとって有用な情報を定期的に発信しております。
現在、登録してくださった方には当ブログのオリジナル教材「数学の論理」を無料でプレゼントさせていただいています。
40ページ以上の少し長めの教材ですが、教科書には載っていない必須級の情報を詰め込んだ教材なので、ぜひ最後まで目を通してみてください。(教材の詳しい説明はこちら)
LINE公式アカウントのご登録は以下のボタンからお願いいたします。

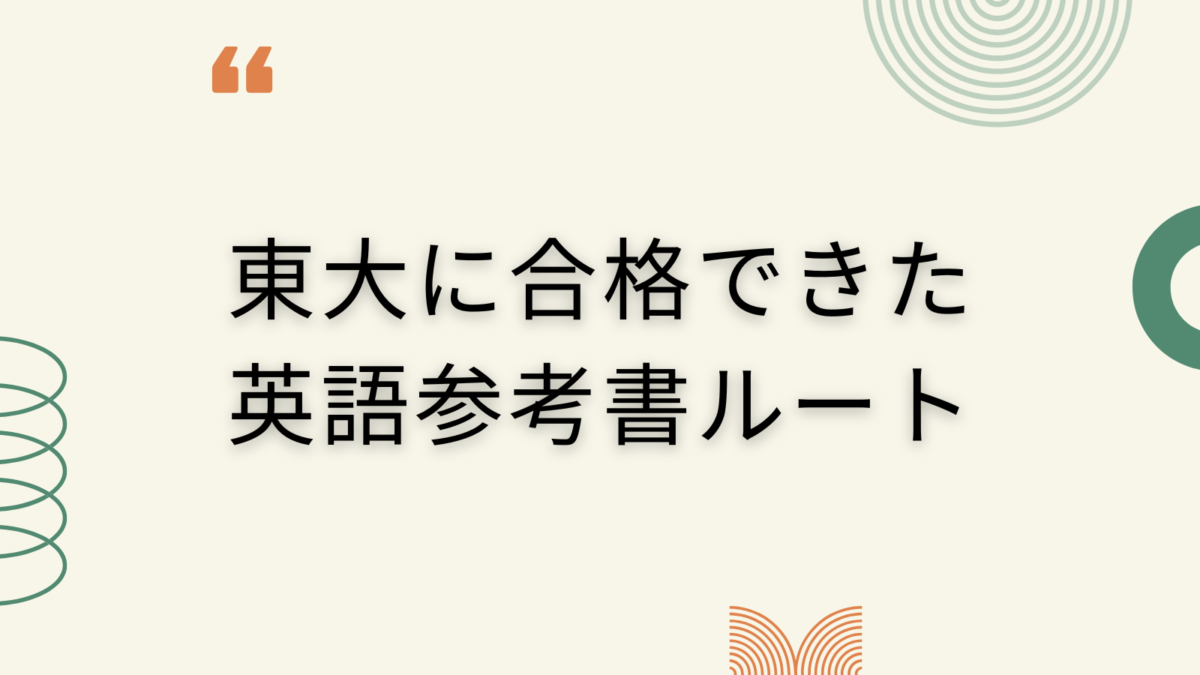


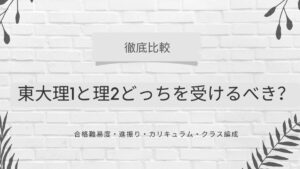
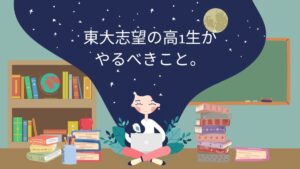
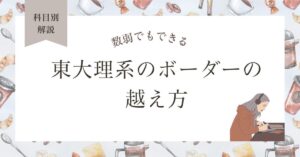


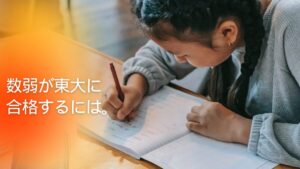
コメント