英語の学習では毎日英語に触れ続けることが最も重要です。
そのための題材としては様々なものがありますが、英語に関して言えば最強の題材は過去問だと思います。
他の科目であれば難易度がまだ高すぎたりといった問題もありますが、英語に関しては英文法や英単語を覚えていれば、東大の過去問であっても時間をかければ読むことができるからです。
むしろ過去問を普段の演習材料に用いることで、英語脳に切り替える練習をしつつ、本番の文章の難易度や問題形式を肌で感じて慣れることができます。
私も市販の長文問題集などは一冊もやらずに過去問を使っていましたが、東大模試では90点台までは出したことがあります。
もちろん、帰国子女ではありません。
今回は、東大受験生にとって最強の題材である東大過去問を25年分集めた「東大の英語25カ年」の特徴・使い方を解説していこうと思います。
なお、東大対策の参考書ルートが知りたい方は以下の記事をチェックしてください。
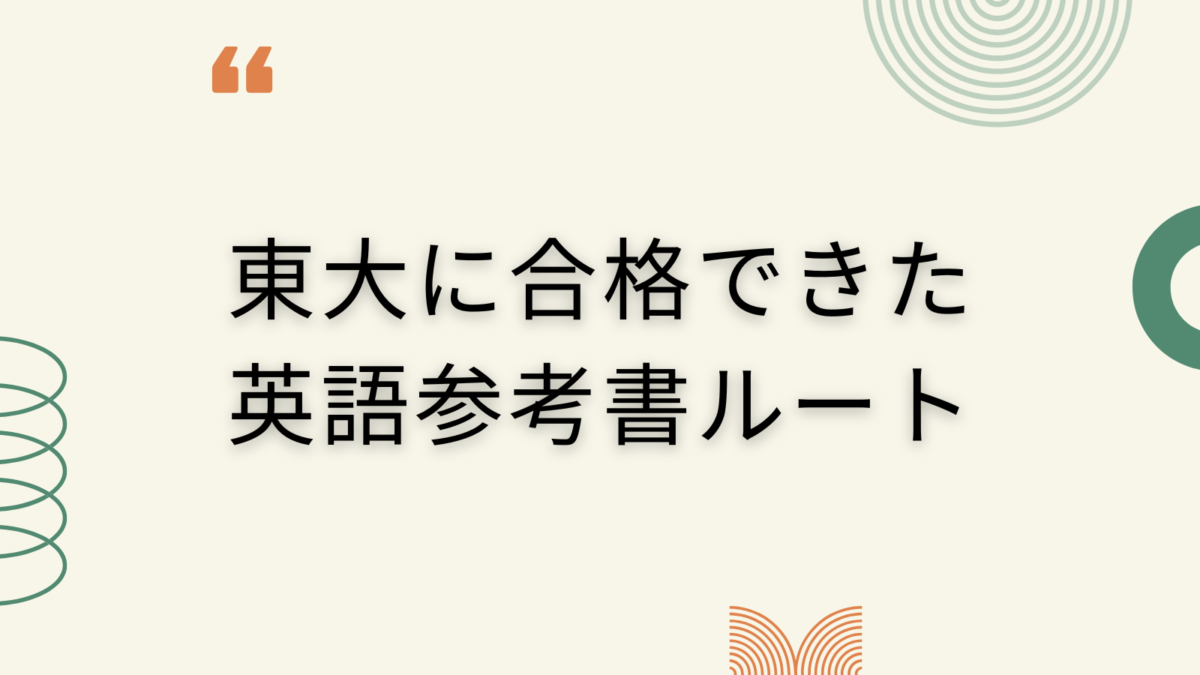
 牛タン
牛タン東大志望必見だよ!
本書の特徴


本書はその名の通り、東大英語の過去問を25年分集めて解説を付した本です。
ただし、年ごとではなく大問ごとに問題がまとめられていることに注意してください。
したがって、年度ごとに問題を解くのには不向きで、あくまで題材が東大の過去問のみの問題集のようなイメージでしょう。
また、著者は駿台の人気講師であり「英作文の鬼」の異名をもつ竹岡博信先生です。
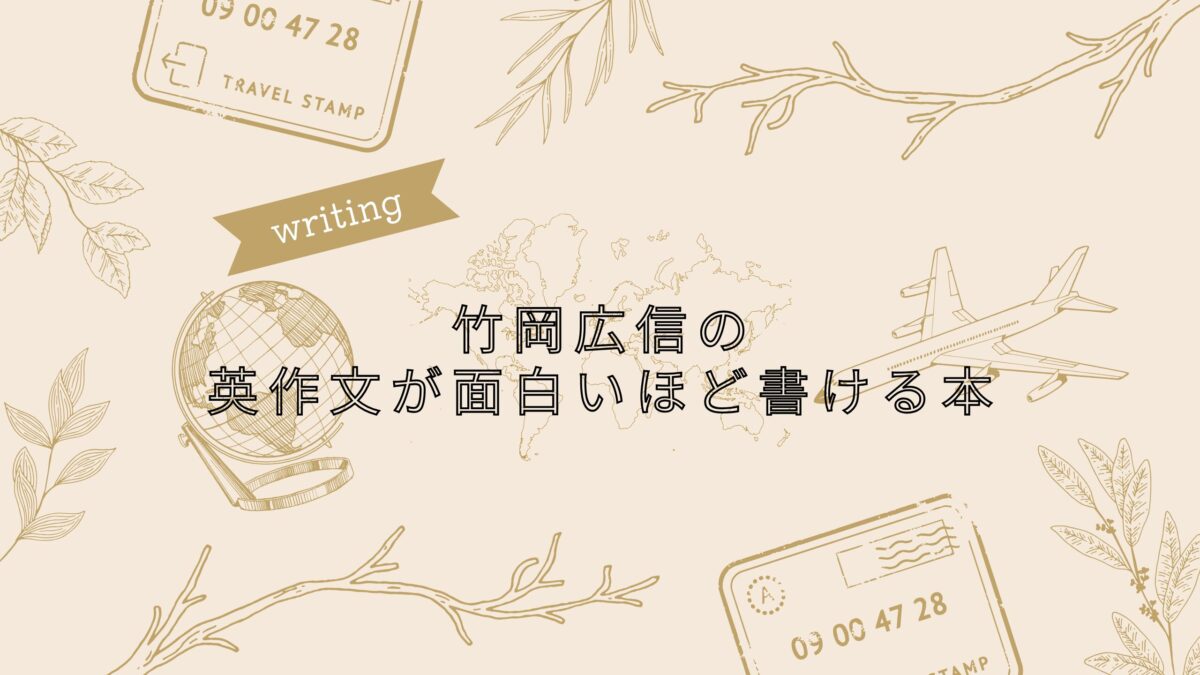
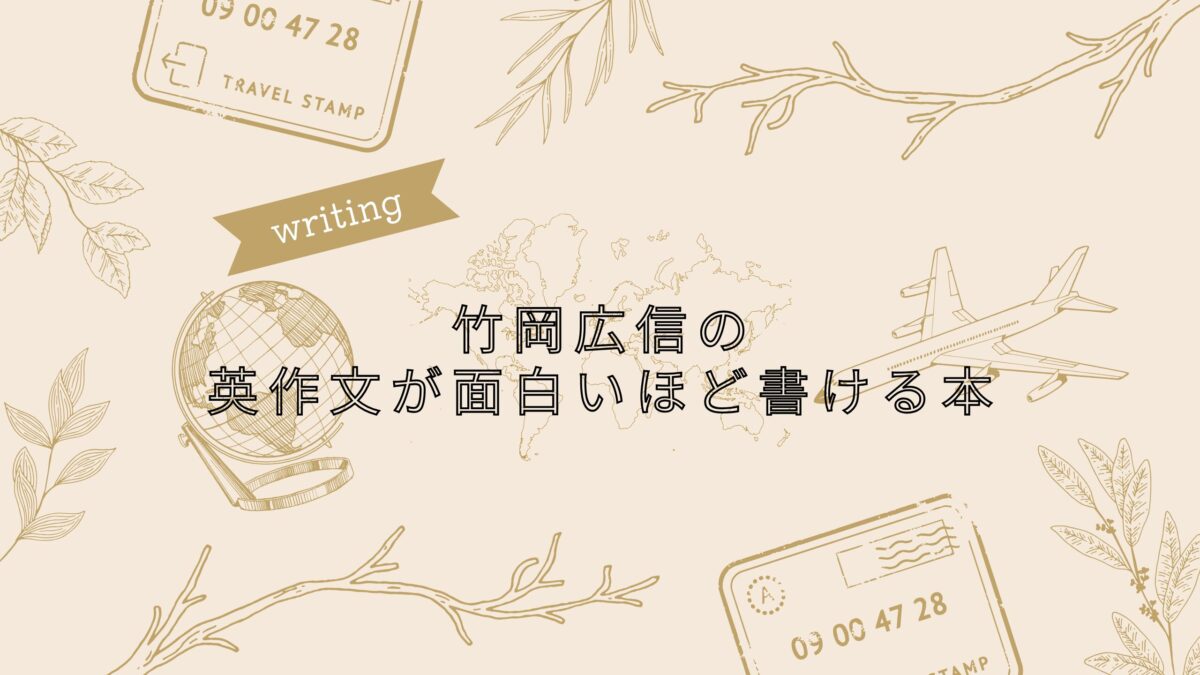
使い方のポイント


大問ごとに解く
先述の通り、この本は年毎に時間を測ってセットでやるための参考書ではありません。
自分が強化したい大問や練習したい大問に集中して取り組みましょう。
各大問の特徴については後で詳しく解説していきます。
直近10年は残しておく
次に大切なことが、直近10年分ほどはやらずに残しておくことです。
なぜなら、実際の入試と同じように時間を測って1年分一気に解く練習も必要だからです。
どの程度のスピード感で解けばよいのかを体にしみこませることで、本番でも焦らずに問題に対処することができるでしょう。
直近10年ほどの問題に関しては、単なる問題演習に使うのではなく、過去問を印刷して時間を測って解くことをおすすめします。
どんどん解く
25年分もの過去問があると、問題に対して「もったいない」という気持ちは全く不要です。
25年分って、思ったより全然多いものですよ。
直近10年を残したとしても15年分もあります。
私も高3の夏~秋ぐらいにこの本を買ってちょくちょく進めていたんですが、上にあげた「竹岡博信の英作文が面白いほど書ける本」などの参考書をやったり、他科目の勉強に追われたりしているうちに、いつの間にか入試本番でした。
この記事を読んでいるあなたが今高3の方であれば、この本だけ毎日やり続けるとかでなければ、問題がなくなってしまうこともないと思います。
また、もしすべての問題が解き終わってしまったとしても、もう一周やればよいのです。
以外と内容を覚えていないことが多いです。
仮になんとなく内容を覚えていたとしても、英語の学習は解けるか解けないかというより読んだり書いたりすることそのものの練習という側面が強いため、復習はかなり効果的だと思います。
私も以前に解いた問題を何回か解いていましたよ。
大問ごとの特徴


「東大の英語25カ年」に取り組むにあたって、どの大問からやればよいのか分からないという方もいるでしょう。
基本的には自分の強化したい部分をやることになりますが、あまりこだわらなくてよい大問もあったりします。
そこで、ここでは東大英語の大問ごとの特徴について解説していきましょう。
1(a) 要旨要約
1(a)は短めの英文を読んで日本語で要約する問題です。
英文の難易度は優しめなので、初めて過去問を解くならこの大問が解きやすいかもしれません。
文章自体も短いので、内容がつかめていれば特別な手法を使わなくても解けます。



あまり時間時間が取れない日に、英語に触れるという意味でこの大問によく取り組んでいました。



短い文章でもいいから、英語に毎日触れることは大切だね!
1(b) 読解
1(b)は欠文補充や段落整序といった、文章全体の論理の流れをつかめているかを問う問題が出題されます。
文章読解力をダイレクトに問われる試験ともいえるでしょう。
癖が少ない入試で良く出題されるような文章を扱っていることもあり、この大問を練習することは併願校やセンター試験含めた入試全般の対策につながります。
他の問題は年度によって異なりますが、無秩序に並べられた英単語を並び替えて一つの文にする問題がよく出題されています。
このタイプの問題は難しいことが多いので、分からなければさっさと飛ばして最後に戻ってきて考えるのがおすすめです。
2(a) 自由英作文
2(a)は自由英作文です。
昔はヘンな問題が多かったのですが、最近はまともな問題が増えてきたので対策がしやすくなっています。
先述の通り、本書は「英作文の鬼」が解説を書いてくれているので、次の2(b)とともにしっかり解いて解説を読み、便利な表現はどんどんインプットしていくとよいでしょう。
2(b) 和文英訳
2(b)は和文英訳です。
英訳しにくい文章が出ることが多いので、簡単な日本語に言い換える力が重要です。
上で紹介した「竹岡博信の英作文が面白いほど書ける本」とこの過去問で竹岡先生が紹介している表現を1個ずつマスターしていけば、たいていの日本語は大意を違えずに英語にできると思います。
3 リスニング
大問3はリスニングなのですが、この本にはリスニングは収録されていないので注意してください。
同じシリーズで「東大の英語リスニング20カ年」という参考書もあるのですが、リスニングはあまり遡りすぎると近年の傾向とずれるのでおすすめしません。
具体的に言うと、昔の方が簡単で、選択肢も少ない(2018年以降4つから5つに増加)です。
2018以降の問題はどうせ年度ごとに時間を測ってやることになると思うので、わざわざ20年分も入ったこの本を買う意味がないわけです。
そこで、代わりにおすすめしたいのが、「キムタツの東大英語リスニング」です。
東大受験生は結構な割合で使っている印象で、問題難易度や選択肢の数も近年の傾向に沿っているので問題演習として最適です。



私も受験生時代にお世話になった本です!
4(a) 文法
大問4(A)は、長文の中の下線部から誤りを発見する問題です。
大問3と同じく選択肢が用意されています。
ただ、難易度が高いので、東大生の中でも適当に選択肢を選んでいたという人が結構おり、対策は正直後回しで構いません。
本番では基本的な文法知識で解ける問題だけ素早くさらって、あとは適当に選択肢をマークしておけば大丈夫です。
4(b) 英文和訳
4(b)は英文和訳です。
東大英語に挑戦する段階にいるならこの問題はある程度解けなければなりません。
なぜなら、英語の基礎力がそのまま表れるからです。
単塾語や文法が分かったうえで構文を把握するという英語の基礎中の基礎を問われています。
この大問が全然分からないようでは、他の大問も解けない、または時間が非常にかかるはずです。
当ブログで紹介している勉強法ルートでも単語と文法の後に必ず英文和訳(=英文解釈)の練習はやるようにと言っています。
もしまだ英文和訳の練習をしたことがない方がいれば、以下の記事で勉強法やおすすめ参考書について解説しているので今すぐご覧ください。


逆に言うと、この本に取り組むまでに英文解釈ができるようになっている人は、そこまで対策しなくてもよい大問だと思います。
5 小説読解
最後は小説読解です。
普段は英語の小説など読んでいる人の方が少ないと思うので、よくわからない表現もたくさん出てくるでしょう。
それらは読み飛ばしてしまって、大体の流れをつかめるように素早く、楽しく読んでいきます。
そこまでの高得点は取れなくてもここまでの大問である程度取れていれば及第点には達するはずですが、小説に慣れておくためにもそこそこには対策しておきましょう。
まとめ
東大の問題は英作文の問題に癖があったり物語が出題されたりと個性的な部分もありますが、基本的な知識があれば解ける問題がほとんどです。
東大受験生の方は「東大の英語25カ年」で日々の英語学習に過去問を取り入れて、早いうちから過去問に慣れておくのがおすすめです。
LINE公式アカウントのご紹介
当ブログのLINE公式アカウントでは、受験生の方にとって有用な情報を定期的に発信しております。
現在、登録してくださった方には当ブログのオリジナル教材「数学の論理」を無料でプレゼントさせていただいています。
40ページ以上の少し長めの教材ですが、教科書には載っていない必須級の情報を詰め込んだ教材なので、ぜひ最後まで目を通してみてください。(教材の詳しい説明はこちら)
LINE公式アカウントのご登録は以下のボタンからお願いいたします。

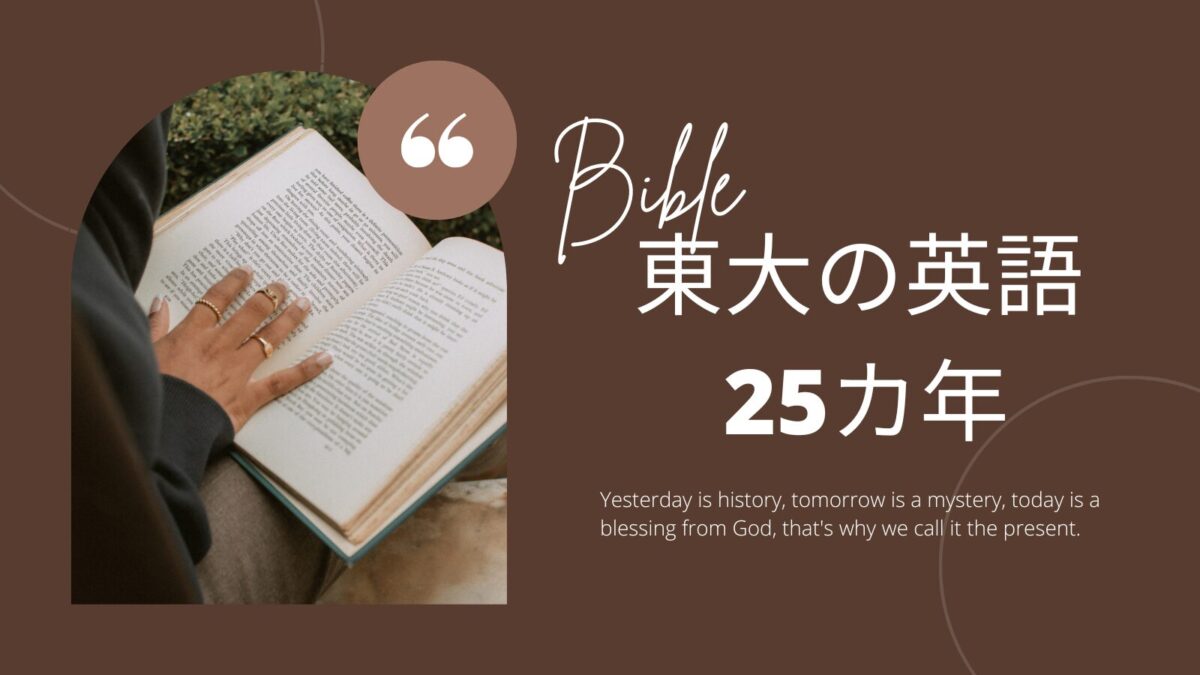


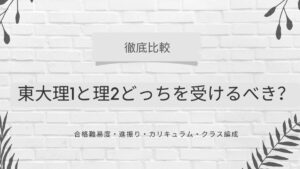
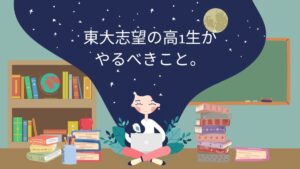
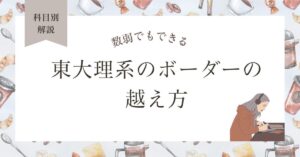


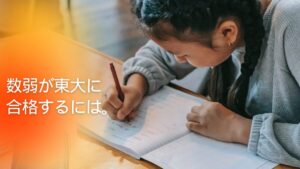
コメント